リビングラボ・トーク/『はじめてのリビングラボ』関連ページ
2026.01.04
はじめてのリビングラボ関連イベント リビングラボ・トーク(Living Lab Talk)
■当面のリビングラボ・トーク
・12/20(火) 屋冨祖通り会・NTTドコモ共催 in 沖縄 ・1/28(水) ミラツク/エッセンス 西村勇也さん共催 in京都未来庵 ・2/2(月) リビングラボ・トーク 特別編 スマートシティを考える スマートシティ・インスティテュート・ジャパン共催 ・3/14(土) リビングラボ・トーク w/みんラボ 原田悦子さん、須藤智さん共催
■開催済・公開中のリビングラボ・トーク
・【記事】12/17(水) 尼崎おせっかい会議実行委員会共催 in尼崎 ・【取材記事】11/16(日)Deep care Lab 川地さん/田島さん in應典院 w/おわりのケア展(大阪府天王寺) ・【動画公開中】11/11(火)UR都市機構 URBANG TABLE共催企画 in天神 ・【レポート公開中】10/21(火) KOEL Design Studio 田中友美子さん in 大手町 ・【Podcast公開中】8/22(金)17:25-17:55渋谷でDeathラジオ 〜生も死も、ウェルビーイングに〜 # 72「リビングラボ from Deathの可能性」 ・8/17(日)14-15時 リビングラボ・トーク 特別編(in 霞が関)(立命館大学 上平さんとのセッション) ・【レポート公開中】7/20(日) 13-18時 リビングラボ・トーク in 西粟倉&むらまるごと研究所5周年記念シンポジウム ・【Podcast公開中】7/7(月)20:30-21:30 リビングラボ・トーク in Voicyなのだ ・【レポート公開中】6/11(火)18-19時 リビングラボ・トーク in 神山(徳島県神山町の皆さんとのセッション) ・【レポート公開中】6/2(月)15-17時 リビングラボ・トーク in 霞が関(東京大学葛岡先生とのセッション、官民共創ハブ川島さんご協力) ・【レポート公開中】6/1(日)11-12時 リビングラボ・トーク in 梅田(関西学院大イノベーション研究会のみなさんとのセッション) ・【レポート公開中】5/19(月)18-19時 リビングラボ・トーク in 千葉(千葉工業大学 柴田さん、新井田さんとのセッション) ・【Podcast公開中】5/28~ リビングラボ・トーク in Muture Podcast 公開中(Muture CEO 莇大介さんとのセッション)■イベント情報をご希望の方へ
※「JNoLLリビングラボ・メーリングリスト」(月1程度):書籍イベント含めた国内のLLイベント情報をご希望の方はこちらのフォームよりご登録ください。※「はじめてのリビングラボ」ニュースレター(不定期):書籍の中身やイベントに関するつぶやきをご希望の方は、こちらのフォームよりご登録ください。
みらいの社会を、
みんなでつくる!
日本初のリビングラボ書籍「はじめてのリビングラボ」紹介ページ
組織やセクターを超えた共創が求められる時代に
市民、行政、企業、大学にいる人たちがどのように暮らしの中でともに実験するのか。
さまざまな価値観が対立する社会のなかで
みんなで答えを探す、希望のデザインアプローチ。
■リビングラボ (Living Lab)とは?
リビングラボとは、暮らし( L i v i n g )と実験室( L a b s )を組み合わせた言葉で、市民や企業、公共機関、大学などが協働して社会課題の解決や新しい価値を生み出すための仕組みです。■書誌情報
『はじめてのリビングラボ──「共創」を生みだす場のつくりかた』
木村篤信,安岡美佳 著
出版社:NTT出版
発売日:2025.4.1
Amazonで購入する
■著者紹介
木村篤信
地域創生Co デザイン研究所(NTT グループ)ポリフォニックパートナー。 一般社団法人 日本リビングラボネットワーク代表理事。東京理科大学客員准教授。大阪大学、奈良先端科学技術大学院大学を修了後、NTT 研究所に入社。HCI、CSCW、UXデザイン、デザイン思考の研究を経て、ソーシャルデザイン研究PJを立ち上げる。これまでの国内外での共同研究や多数のリビングラボ実践を踏まえ、現在は、日本各地の市民協働PJ、企業のオープンイノベーションPJ、行政のウェルビーイング政策デザインに関わる。博士(工学)。主な書籍に、『2030年の情報通信技術生活者の未来像」(NTT 出版)など。
安岡美佳
ロスキレ大学准教授。 北欧研究所代表。京都大学大学院情報学研究科修士課程修了、東京大学工学系先端学際工学専攻を経て、2009年にコペンハーゲンIT 大学で博士号取得。コペンハーゲンIT 大学助教授、デンマーク工科大学リサーチアソシエイツ等を経て現職。2005年から北欧と日本の2拠点で研究活動を実施。専門はユーザー中心設計、デザインイノベーションの共創手法(参加型デザイン、リビングラボ等)、AI・ロボットを含めたIT の社会実装など。2000年代からデジタルシティの研究に関わる。主な書籍に、『北欧のスマートシティ』(学芸出版社)など。
■本書の活用方法
本書では、リビングラボを知らない人にも、知っているけれども、うまく共創ができないと悩んでいる人にも読んでもらえるように執筆しました。リビングラボは、産官学民のマルチステイクホルダーが関わる取り組みになるため、サービス開発で社会的なインパクトを生みだしたい企業のビジネスマン、テクノロジーの社会実装で悩む大学等の研究者、人口減少に直面する地方で課題と対峙する公共機関の職員、自らのまちの課題を自分事として向き合う当事者の皆さん、それぞれの目線から読める内容としました。
具体的には、リビングラボの全体像をつかんでいただくことを狙いとして、第1部では、どんなところで、何ができる「場」なのか、そしてなぜいまリビングラボが注目されているのかについて紹介しました。第2部では、リビングラボを始めたいと思う人に向けて、具体的なプロセスと実践のための手法を解説しました。さらに、その根底にあるリビングラボが生まれた文化的背景やそこで育まれた思想を学ぶことで、リビングラボへの理解が深まることをめざしました。第3部では、読者の実際の興味に近いリビングラボを参照できるよう、バリエーションのある事例を選定し、紹介しました。リビングラボの本場とも言える北欧の事例と、北欧とは異なる文化的背景の中で試行錯誤してきた日本やアジアの事例を掲載しています。
本書は、入門書のため、実践する際に役立つ知識やコツといったことには、ページを十分に割けませんでした。これからリビングラボを実践していくみなさんは、さまざまな壁にぶつかるとは思いますが、そうした際に役立つ、実践知をまとめた『リビングラボの手引き』(2018年)という冊子を紹介したいと思います。本書で学んだ方法論と実践のギャップを、手引きで埋めながら、さらにみなさんが自ら見つけた実践知をフィードバックしていただければ、リビングラボがますます充実していきます。以下よりアクセスして、併せてご活用ください。
また、当時、海外で提唱されたリビングラボを、日本の文化的背景を踏まえながらアップデートしたり、自分たちの文脈で活用しようとする動きは生まれていませんでした。そこで筆者らは、日本のリビングラボの実践者や研究者と対話しながら、日本の文脈においてリビングラボを深めて発展させていくために、「一般社団法人日本リビングラボネットワーク」を設立しています。
欧州の文脈で開発・発展してきたリビングラボを、日本の文脈において捉えなおす共同研究や、学術的に蓄積された知見をもとに人材育成や啓発活動に取り組んだり、リビングラボに関心のある人たちが実践知や研究知見を共有し対話できるネットワーキングの場づくりを行っています。また、欧州リビングラボネットワーク(ENoLL)や韓国リビングラボネットワーク(KNoLL)などの海外のコミュニティとも連携しながら、お互いの知見も共有する機会もつくっています。興味を覚えた方はご参加ください。
■目次
はじめに第1部 ようこそリビングラボへ
第1章 リビングラボってどんなところ? 1.リビングラボとは?( 1 )リビングラボは生活の場で実施される
( 2 )リビングラボでは誰もが専門家
( 3 )リビングラボはみんなで共創する場
2.リビングラボにまつわる誤解
( 1 )リビングラボとはメソッドである?
( 2 )リビングラボとは建物である?
( 3 )リビングラボとは当事者のためのものである?
第2章 リビングラボでなにができるのか? 1.リビングラボでできること
( 1 )モノづくりとコトづくり
( 2 )みんなで一緒につくること
( 3 )当事者マインドの醸成と身体化
2.リビングラボは誰のもの?
( 1 )当事者として関わる
( 2 )企業として関わる
( 3 )公共機関として関わる
( 4 )研究者として関わる
第3章 リビングラボはなぜいま注目されているのか? 1.なぜ、今の社会はイノベーションを求めるのか?
( 1 )加速し、多様化する社会
( 2 )リビングラボはイノベーションをもたらす仕組み
2.なぜ、テクノロジーに向き合うことが必要なのか?
( 1 )テクノロジーは後戻りしない
( 2 )リビングラボはテクノロジーをひらく
3.なぜ、みんなの参加が必要なのか?
( 1 )一体化する世界、多様化する個人
( 2 )リビングラボは、参加型アプローチで、多様性を受容する
第2部 リビングラボを学ぶ
第4章 リビングラボのプロセス 1.二つのリビングラボ( 1 )仮説検証型リビンクラボ
( 2 )仮説探索型リビングラボ
2.リビングラボの七つのプロセス
( 1 )プロジェクト定義
( 2 )対話・相互理解
( 3 )課題設定
( 4 )アイデア創出
( 5 )プロトタイピング
( 6 )実験的テスト
( 7 )社会実装テスト
3.リビングラボの流れ― 子育てアプリの事例をつうじて
① 子育てにおける孤立― プロジェクト定義
② 子育て当事者の実態を知る― 対話・相互理解
③ 安心して自分に向き合えること― 課題設定
④ 子育てアプリ― アイデア創出
⑤ 実物大で触れるスマホ画面イメージ― プロトタイピング
⑥ 子育て中の人を集めて試してもらう― 実験的テスト
⑦ 子育て中の生活環境下で使ってもらって評価する― 社会実装テスト
第5章 リビングラボの手法 1.リビングラボと手法の関係性
2.リビングラボの七つの手法とツール
( 1 )プロジェクト定義のための手法
① バリュートライアングル/ ② リソースマトリックス
( 2 )対話・相互理解のための手法
② 哲学対話/ ④ リッチピクチャー
( 3 )課題設定のための手法
⑤ 半構造化インタビュー/ ⑥ 行動観察/ ⑦ 因果的階層分析
( 4 )アイデア創出のための手法
⑧ 二段階ブレスト/ ⑨ K J 法/ ⑩Generative tool kit
( 5 )プロトタイピングのための手法
⑪ コンテクスチュアル(文脈的)プロトタイピング/ ⑫ エクスペリエンス(体験的)プロトタイピング/⑬ ファンクショナル(機能的)プロトタイピング
( 6 )実験的テストのための手法
⑭ ユーザビリティテスト/ ⑮ 思考発話法
( 7 )社会実装テストのための手法
⑯ ダイアリー法/ ⑰ 包括的評価ツール
第6章 リビングラボの歴史的背景 1.近代科学の専門化
2.リビングラボの三つの系譜
( 1 )シチズンサイエンス
( 2 )ユーザ中心設計
( 3 )参加型デザイン
3.リビングラボの発展と普及
( 1 )ヨーロッパにおけるリビングラボ
( 2 )日本におけるリビングラボ
( 3 )これからの社会に求められるリビングラボ
第3部 リビングラボを見学する
10のケーススタディ注目したいポイント
c a s e 1 コペンハーゲンストリートラボ
c a s e 2 エグモント・ホイスコーレ
c a s e 3 E U 2 0 2 0 R E A C H プロジェクト
c a s e 4 ノルウェーE V ネットワーク
c a s e 5 デモクラシー・ガレージ
c a s e 6 みんなの使いやすさラボ
c a s e 7 おやまちリビングラボ
c a s e 8 大牟田リビングラボ
c a s e 9 O n L A B
c a s e 10 鎌倉リビングラボ
おわりに
Amazonから購入
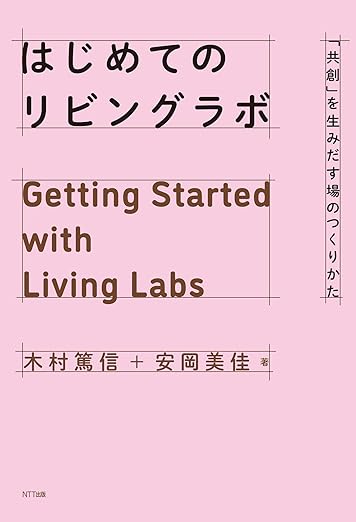
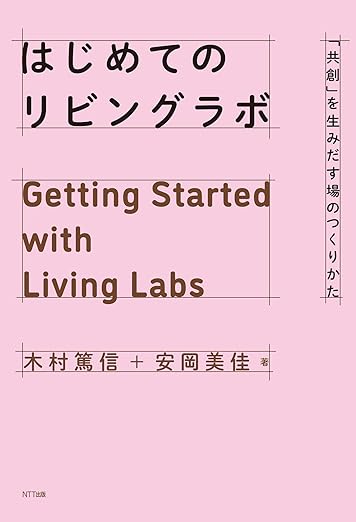
はじめてのリビングラボ関連イベント リビングラボ・トーク(Living Lab Talk)
■当面のリビングラボ・トーク
・12/20(火) 屋冨祖通り会・NTTドコモ共催 in 沖縄 ・1/28(水) ミラツク/エッセンス 西村勇也さん共催 in京都未来庵 ・2/2(月) リビングラボ・トーク 特別編 スマートシティを考える スマートシティ・インスティテュート・ジャパン共催 ・3/14(土) リビングラボ・トーク w/みんラボ 原田悦子さん、須藤智さん共催
■開催済・公開中のリビングラボ・トーク
・【記事】12/17(水) 尼崎おせっかい会議実行委員会共催 in尼崎 ・【取材記事】11/16(日)Deep care Lab 川地さん/田島さん in應典院 w/おわりのケア展(大阪府天王寺) ・【動画公開中】11/11(火)UR都市機構 URBANG TABLE共催企画 in天神 ・【レポート公開中】10/21(火) KOEL Design Studio 田中友美子さん in 大手町 ・【Podcast公開中】8/22(金)17:25-17:55渋谷でDeathラジオ 〜生も死も、ウェルビーイングに〜 # 72「リビングラボ from Deathの可能性」 ・8/17(日)14-15時 リビングラボ・トーク 特別編(in 霞が関)(立命館大学 上平さんとのセッション) ・【レポート公開中】7/20(日) 13-18時 リビングラボ・トーク in 西粟倉&むらまるごと研究所5周年記念シンポジウム ・【Podcast公開中】7/7(月)20:30-21:30 リビングラボ・トーク in Voicyなのだ ・【レポート公開中】6/11(火)18-19時 リビングラボ・トーク in 神山(徳島県神山町の皆さんとのセッション) ・【レポート公開中】6/2(月)15-17時 リビングラボ・トーク in 霞が関(東京大学葛岡先生とのセッション、官民共創ハブ川島さんご協力) ・【レポート公開中】6/1(日)11-12時 リビングラボ・トーク in 梅田(関西学院大イノベーション研究会のみなさんとのセッション) ・【レポート公開中】5/19(月)18-19時 リビングラボ・トーク in 千葉(千葉工業大学 柴田さん、新井田さんとのセッション) ・【Podcast公開中】5/28~ リビングラボ・トーク in Muture Podcast 公開中(Muture CEO 莇大介さんとのセッション)■イベント情報をご希望の方へ
※「JNoLLリビングラボ・メーリングリスト」(月1程度):書籍イベント含めた国内のLLイベント情報をご希望の方はこちらのフォームよりご登録ください。※「はじめてのリビングラボ」ニュースレター(不定期):書籍の中身やイベントに関するつぶやきをご希望の方は、こちらのフォームよりご登録ください。
みらいの社会を、
みんなでつくる!
日本初のリビングラボ書籍「はじめてのリビングラボ」紹介ページ
組織やセクターを超えた共創が求められる時代に
市民、行政、企業、大学にいる人たちがどのように暮らしの中でともに実験するのか。
さまざまな価値観が対立する社会のなかで
みんなで答えを探す、希望のデザインアプローチ。
■リビングラボ (Living Lab)とは?
リビングラボとは、暮らし( L i v i n g )と実験室( L a b s )を組み合わせた言葉で、市民や企業、公共機関、大学などが協働して社会課題の解決や新しい価値を生み出すための仕組みです。■書誌情報
『はじめてのリビングラボ──「共創」を生みだす場のつくりかた』
木村篤信,安岡美佳 著
出版社:NTT出版
発売日:2025.4.1
Amazonで購入する
■著者紹介
木村篤信
地域創生Co デザイン研究所(NTT グループ)ポリフォニックパートナー。 一般社団法人 日本リビングラボネットワーク代表理事。東京理科大学客員准教授。大阪大学、奈良先端科学技術大学院大学を修了後、NTT 研究所に入社。HCI、CSCW、UXデザイン、デザイン思考の研究を経て、ソーシャルデザイン研究PJを立ち上げる。これまでの国内外での共同研究や多数のリビングラボ実践を踏まえ、現在は、日本各地の市民協働PJ、企業のオープンイノベーションPJ、行政のウェルビーイング政策デザインに関わる。博士(工学)。主な書籍に、『2030年の情報通信技術生活者の未来像」(NTT 出版)など。
安岡美佳
ロスキレ大学准教授。 北欧研究所代表。京都大学大学院情報学研究科修士課程修了、東京大学工学系先端学際工学専攻を経て、2009年にコペンハーゲンIT 大学で博士号取得。コペンハーゲンIT 大学助教授、デンマーク工科大学リサーチアソシエイツ等を経て現職。2005年から北欧と日本の2拠点で研究活動を実施。専門はユーザー中心設計、デザインイノベーションの共創手法(参加型デザイン、リビングラボ等)、AI・ロボットを含めたIT の社会実装など。2000年代からデジタルシティの研究に関わる。主な書籍に、『北欧のスマートシティ』(学芸出版社)など。
■本書の活用方法
本書では、リビングラボを知らない人にも、知っているけれども、うまく共創ができないと悩んでいる人にも読んでもらえるように執筆しました。リビングラボは、産官学民のマルチステイクホルダーが関わる取り組みになるため、サービス開発で社会的なインパクトを生みだしたい企業のビジネスマン、テクノロジーの社会実装で悩む大学等の研究者、人口減少に直面する地方で課題と対峙する公共機関の職員、自らのまちの課題を自分事として向き合う当事者の皆さん、それぞれの目線から読める内容としました。
具体的には、リビングラボの全体像をつかんでいただくことを狙いとして、第1部では、どんなところで、何ができる「場」なのか、そしてなぜいまリビングラボが注目されているのかについて紹介しました。第2部では、リビングラボを始めたいと思う人に向けて、具体的なプロセスと実践のための手法を解説しました。さらに、その根底にあるリビングラボが生まれた文化的背景やそこで育まれた思想を学ぶことで、リビングラボへの理解が深まることをめざしました。第3部では、読者の実際の興味に近いリビングラボを参照できるよう、バリエーションのある事例を選定し、紹介しました。リビングラボの本場とも言える北欧の事例と、北欧とは異なる文化的背景の中で試行錯誤してきた日本やアジアの事例を掲載しています。
本書は、入門書のため、実践する際に役立つ知識やコツといったことには、ページを十分に割けませんでした。これからリビングラボを実践していくみなさんは、さまざまな壁にぶつかるとは思いますが、そうした際に役立つ、実践知をまとめた『リビングラボの手引き』(2018年)という冊子を紹介したいと思います。本書で学んだ方法論と実践のギャップを、手引きで埋めながら、さらにみなさんが自ら見つけた実践知をフィードバックしていただければ、リビングラボがますます充実していきます。以下よりアクセスして、併せてご活用ください。
また、当時、海外で提唱されたリビングラボを、日本の文化的背景を踏まえながらアップデートしたり、自分たちの文脈で活用しようとする動きは生まれていませんでした。そこで筆者らは、日本のリビングラボの実践者や研究者と対話しながら、日本の文脈においてリビングラボを深めて発展させていくために、「一般社団法人日本リビングラボネットワーク」を設立しています。
欧州の文脈で開発・発展してきたリビングラボを、日本の文脈において捉えなおす共同研究や、学術的に蓄積された知見をもとに人材育成や啓発活動に取り組んだり、リビングラボに関心のある人たちが実践知や研究知見を共有し対話できるネットワーキングの場づくりを行っています。また、欧州リビングラボネットワーク(ENoLL)や韓国リビングラボネットワーク(KNoLL)などの海外のコミュニティとも連携しながら、お互いの知見も共有する機会もつくっています。興味を覚えた方はご参加ください。
■目次
はじめに第1部 ようこそリビングラボへ
第1章 リビングラボってどんなところ? 1.リビングラボとは?( 1 )リビングラボは生活の場で実施される
( 2 )リビングラボでは誰もが専門家
( 3 )リビングラボはみんなで共創する場
2.リビングラボにまつわる誤解
( 1 )リビングラボとはメソッドである?
( 2 )リビングラボとは建物である?
( 3 )リビングラボとは当事者のためのものである?
第2章 リビングラボでなにができるのか? 1.リビングラボでできること
( 1 )モノづくりとコトづくり
( 2 )みんなで一緒につくること
( 3 )当事者マインドの醸成と身体化
2.リビングラボは誰のもの?
( 1 )当事者として関わる
( 2 )企業として関わる
( 3 )公共機関として関わる
( 4 )研究者として関わる
第3章 リビングラボはなぜいま注目されているのか? 1.なぜ、今の社会はイノベーションを求めるのか?
( 1 )加速し、多様化する社会
( 2 )リビングラボはイノベーションをもたらす仕組み
2.なぜ、テクノロジーに向き合うことが必要なのか?
( 1 )テクノロジーは後戻りしない
( 2 )リビングラボはテクノロジーをひらく
3.なぜ、みんなの参加が必要なのか?
( 1 )一体化する世界、多様化する個人
( 2 )リビングラボは、参加型アプローチで、多様性を受容する
第2部 リビングラボを学ぶ
第4章 リビングラボのプロセス 1.二つのリビングラボ( 1 )仮説検証型リビンクラボ
( 2 )仮説探索型リビングラボ
2.リビングラボの七つのプロセス
( 1 )プロジェクト定義
( 2 )対話・相互理解
( 3 )課題設定
( 4 )アイデア創出
( 5 )プロトタイピング
( 6 )実験的テスト
( 7 )社会実装テスト
3.リビングラボの流れ― 子育てアプリの事例をつうじて
① 子育てにおける孤立― プロジェクト定義
② 子育て当事者の実態を知る― 対話・相互理解
③ 安心して自分に向き合えること― 課題設定
④ 子育てアプリ― アイデア創出
⑤ 実物大で触れるスマホ画面イメージ― プロトタイピング
⑥ 子育て中の人を集めて試してもらう― 実験的テスト
⑦ 子育て中の生活環境下で使ってもらって評価する― 社会実装テスト
第5章 リビングラボの手法 1.リビングラボと手法の関係性
2.リビングラボの七つの手法とツール
( 1 )プロジェクト定義のための手法
① バリュートライアングル/ ② リソースマトリックス
( 2 )対話・相互理解のための手法
② 哲学対話/ ④ リッチピクチャー
( 3 )課題設定のための手法
⑤ 半構造化インタビュー/ ⑥ 行動観察/ ⑦ 因果的階層分析
( 4 )アイデア創出のための手法
⑧ 二段階ブレスト/ ⑨ K J 法/ ⑩Generative tool kit
( 5 )プロトタイピングのための手法
⑪ コンテクスチュアル(文脈的)プロトタイピング/ ⑫ エクスペリエンス(体験的)プロトタイピング/⑬ ファンクショナル(機能的)プロトタイピング
( 6 )実験的テストのための手法
⑭ ユーザビリティテスト/ ⑮ 思考発話法
( 7 )社会実装テストのための手法
⑯ ダイアリー法/ ⑰ 包括的評価ツール
第6章 リビングラボの歴史的背景 1.近代科学の専門化
2.リビングラボの三つの系譜
( 1 )シチズンサイエンス
( 2 )ユーザ中心設計
( 3 )参加型デザイン
3.リビングラボの発展と普及
( 1 )ヨーロッパにおけるリビングラボ
( 2 )日本におけるリビングラボ
( 3 )これからの社会に求められるリビングラボ
第3部 リビングラボを見学する
10のケーススタディ注目したいポイント
c a s e 1 コペンハーゲンストリートラボ
c a s e 2 エグモント・ホイスコーレ
c a s e 3 E U 2 0 2 0 R E A C H プロジェクト
c a s e 4 ノルウェーE V ネットワーク
c a s e 5 デモクラシー・ガレージ
c a s e 6 みんなの使いやすさラボ
c a s e 7 おやまちリビングラボ
c a s e 8 大牟田リビングラボ
c a s e 9 O n L A B
c a s e 10 鎌倉リビングラボ
おわりに
Amazonから購入